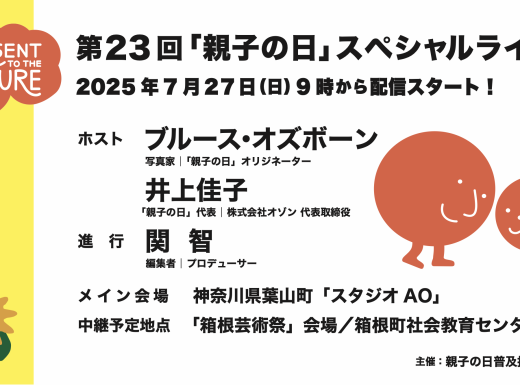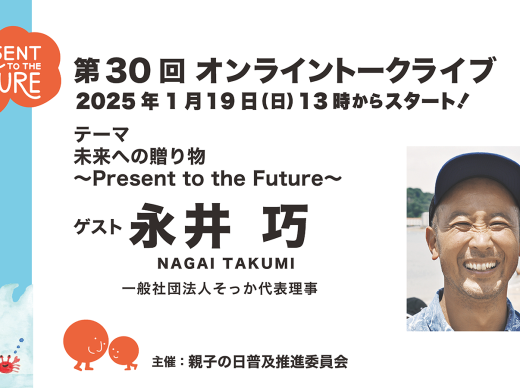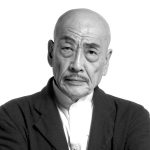親子の日 エッセイコンテスト 2025 入賞作品
開催・応募期間:2025年5月1日〜8月31日
グランプリ・親子の日特別賞
- カオハガンキルトラグと写真絵本「たいせつなもの」
「ゆなちゃんは手のかからない良い子ね」
その言葉が呪縛だった。田舎の家の長女として生まれた私にとって私の評判は家の評判だった。教育熱心な親は小学校に入学する前から私を塾に連れて行った。
人より何かを始めるのが早かったおかげで運動も勉強もそれなりにできた。
当たり前のようにテストでいい点数を取ることや部活の大会で入賞するのが私だった。
そうやって私は自分を定義していた。
人懐っこい妹と対照的に、気づけば私と両親の会話は「成果」のことばかりだった。
でもいつまでも完璧に何でもできるわけではない。
一つ成し遂げるともっと何か成し遂げなければと新しいことに手を出す。
それを続けるうちに私は壊れてしまった。
不登校になったのだ。
毎晩明日の学校が不安で寝付けなかった。
朝起きて制服を着ても玄関から出れなかった。
それを母が心配そうに見ているのが苦しかった。
「休んでもいいよ」そう言われるたびに母の信頼を裏切っている気がした。
自慢の娘じゃなくなっていく気がした。
不登校になったことを何事でもないかのように食卓で振る舞う父を見ては不安になった。
苦しさを物に当たった。
そんな時でも両親は私を諦めなかった。
昼夜逆転して1人で過ごすことが多くなったときは、母は一緒に起きて韓国ドラマを見てくれた。朝起きれた日はドライブに連れ出してくれた。
父は私がやりたいことができるようにあえて遠くから見守ってくれるようになった。
「通信制高校に行きたい」と言った日は何も言わず頷いてくれた。
何もできなくなっても変わらず傍にいてくれた。
不登校だった時間を通して、私は父と母のことをよく知れた気がする。
二人は想像以上に私のことを知っていて、愛している。
今はそれを十分理解しているから完璧じゃない自分も愛せる。
お父さん、お母さん、私の子育ては人一倍手が掛かったと思います。
予想外のことだらけだったと思うけど、その分たくさん思い出もあります。
ありがとう。
DAC賞
- Fruity Weekend ジュースセット
「きょう泣いちゃうかもしれんなあ」
月曜の朝。4歳の娘あかりが、腕組みをして首をかしげながら言った。
最近おませになった喋り方と、子供らしい不安とのギャップに、私は思わず笑いそうになる。
働くママを持つ子にとって、月曜の朝は試練だ。
保育園に着くと、「ママがいい」という泣き声が、あちこちから聞こえる。
週末をママとたっぷり過ごした子ども達は、月曜の朝がたまらなく寂しい。
娘も、3歳頃までは毎週のように泣いていた。
その泣き声を背中で聞きながら、胸がきゅっとなって、仕事へ向かったものだった。
でも今は、ママが仕事に行かなくちゃいけないことも、友達と遊んでいたら楽しい気持ちになることも、ちゃんとわかっている。
だからもう泣かない。
でも、寂しくないわけではない。
土日、たくさん一緒に遊んだもんね。泣かないけど、寂しいよね。
ママ、あかりの気持ち、ちゃんとわかってるからね。
そんな朝、娘が決まって言うことばがある。
「ママ、からあげつくって」
大好きなからあげがあるから頑張れる、というのもあるだろう。
でも、それ以上に「ママが自分のことを思って作ってくれる」ことが、力になるんだと思う。
これから娘も大きくなって、いろんな壁にぶつかるだろう。
今は何でも話してくれるけれど、話したくないことも出てくるかもしれない。直接私の言葉で励ましてあげられることも、減っていくだろう。
そんな時、きっと私は、「がんばれ。あかりなら大丈夫。ママはいつでも味方だよ」という言葉のかわりに、からあげを揚げる。
「わかった。美味しいからあげ作るね」
そう言うと、娘はぱっと花が咲いたようににっこり笑い、教室へと歩き出す。
頼もしい後ろ姿に、成長の嬉しさと、大きくなっていく寂しさを感じながら、私は今日も、揚げる。
とびきりジューシーな愛を、からあげにこめて。
CHOYA賞
- The CHOYA FRENCH OAK(樽熟成梅酒)
私のおとうさんはもういない。十五歳の時に突然亡くなった。
本当は、それよりもっと前から家にいなくて、単身赴任で遠い土地に行ってしまった。
私が小学二年生の時から、気軽に会えなくなってしまったのだ。そのせいで、おとうさんとの記憶はおぼろげだった。けれど、子どもながらに「弱音を吐いちゃいけないんだ」って、涙を堪えてたことだけは鮮明に覚えている。
ある日、押入れの奥から古いビデオデッキが見つかった。大きくて重い。昔はこれで撮影していたのかと思うと、スマートフォンで何でもできる時代に感謝しなきゃいけないなと思った。そんなことを思いながら、デッキに電源を入れて、入っていたビデオテープを再生してみる。
それは、私の運動会の映像だった。おとうさんと二人三脚をしている、親子競技だ。私は、おとうさんに合わせようと走っている。おとうさんは私に合わせようと走っている。
それが噛み合わない原因になって、少しぎこちない。それでも、おとうさんは真剣に私と走っている。私の肩に置かれた手が大きく見えた。
それで、記憶が蘇にできた。おとうさんは、どんなに忙しくても運動会だけには来てくれていた。練習する時間はないから、本番で息を合わせなくてはならない。私は、それに緊張していたが、おとうさんは楽しそうだった。
今、生きていたら六十七歳になるおとうさん。もう一度、一緒に住みたいという私の願いは叶わなかったけれど、忘れかけていた幼い頃の記憶が、このビデオテープには残っていた。
CHOYA賞
- チョーヤ梅ゼリー
父と月に一回の面会の時、私はどうしても毎回気になって仕方がないことがあった。あまり大きな声では言えないからこっそり教えよう。
それは、父のおなかが会うたびに大きくなっていることだ。
昼寝するときの枕にちょうどいい柔らかさだから、そのおなかは嫌いではなかった。むしろ結構好きだった。でもそれでは父の健康に悪いと思い、会うたびに「痩せな。」というのが習慣だった。
父はそれに対していつも「やっぱり太っちゃったか。
わかった。
次、あう時までに痩せる。」と言うのだ。
しかし、その言葉が本当になることはなかなかない。どうしたら父に痩せてもらえるのだろう。やはり一人暮らしのおじさんは食生活が乱れてしまうのか。ならばどうやって食生活の意識を高めようか。いろいろ考えた結果、私はとある作戦を始めることにした。
その名も、「交換日記大作戦」。
交換日記と言っても、普通の交換日記とは少し違う。
まず、父と私、一つ一冊ずつノートを用意する。そこには必ず日付、その日にあったことの二つを書く。
父はここにプラスで、その日の食事を書く。
そして次の面会の時に交換する。
こうすれば父の食事を監視できる。
そして監視されている父は規則正しい食生活を送ってくれるはず。
この交換日記大作戦は大成功した。父の食生活が改善されたのだ。
これは私が小学生の頃の話だ。
あれから三年以上がたち、スマホを持つようになってからは父との交換日記はしなくなった。
そして最近、父のおなかがまた気になり始めてきた。
仕方ないからもう一度始めてみようか。
交換日記大作戦その2を!
私は、母から「ごめんね」と言われた日のことを今でも鮮明に覚えている。
それは、私が発達障害と知的障害と診断された日のことだった。
それまで母も私自身も「努力すればみんなと同じようにできる」と信じていた。
だから勉強や生活のことでは、ことあるごとに叱られた。
特に学生時代は勉強やテストのことで怒られるのが日常だった。
「なんでそんなにできないの?勉強してないんじゃないの?」
「してるよ!でもできないんだもん!」
泣きながら訴えても「泣くことじゃないでしょ」と叱られる。
そんな負の連鎖の毎日だった。
転機は、大人になってから母と一緒に病院を訪れたときに訪れた。
検査の結果、私は発達障害と知的障害があると診断された。
診断直後、母は私に言った。
「もっと早くわかっていたら、あんなに叱らなかった」
「バカなんて言って、ごめんね」
その瞬間、涙があふれた。あの日を境に、母との心の距離が少しずつ縮まっていった。
今では母は私の特性を理解し、必要なときには「頑張りすぎないでね」「無理しないことが合言葉」と声をかけてくれる。
その言葉は、つい突っ走ってしまう私のブレーキになり、褒めてくれる機会も増えた。
母の言葉が、私の自己肯定感を少しずつ回復させてくれている。
母の謝罪は、私に新しい親子の時間をくれた。
「親子の日」という特別な日に、支えてくれる母への感謝を込めて、このエッセイを綴った。
これもまた、母と私の新しい時間の始まりなのだ。
そして私は今、心から思う。
「お母さん、ありがとう。あなたが私の母でよかった。」
Lingua Franca NY 賞
- ロゴ入り Lingua Franca NY オリジナル商品
幼い頃、私がトイレに行こうとするだけでも泣いて追いかけてきた息子も思春期。
話しかけても煙たがられ、その日の機嫌によっては暴言をはかれ。
あんなに可愛かった息子が・・・男の子の育児は、太く短い?
息子が18歳になったということは、多分に漏れず、私も年齢と共に代謝が落ち、食べれば食べるほど、否、そんなに食べていないにもかかわらず、腹囲以下にばかり肉がつく。
このままではサイズ変更を余儀なくされ、新しい服を購入せざるを得ない。
出費が増える。美容というより節約のため晩御飯を抜くのではなく、少食にする。
「ご飯、今日も食べんの?」
「食べてるやん」
「そんなん、ちょっとやん」
「朝、昼、おやつといっぱい食べてるから大丈夫」
「ダイエットとか、しやんでいいねん。栄養とらな、病気になるやろ!」
「この歳になると、太るから。」
「太ってもええねん!」息子が、本気で怒っている。
普段、いがみあっていても・・・怒りの中に潜む息子の真意を感じて
(私、愛されている)
そう思うと、息子にとって未来永劫 唯一無二の存在、母親っていいなとご飯をおかわり。
円谷プロ賞
- 『ウルトラマンアーク THE MOVIE 超次元大決戦!光と闇のアーク』Blu-ray 特装限定版
隣町で観測史上最高気温41.8℃を記録した夏休みのある日。私は、よく育った浣熊のような長男とちょこまかと動く子狸のような次男を連れて、とある山奥へと向かった。
目的地は「フィッシングセンター」というハイカラな名称を冠したいわゆる釣り堀である。ニジマスとイワナを釣り、塩焼きにしてくれるありがたいレジャースポットであるが、特筆すべきは「イワナのつかみ取り」を体験できることにある。浣熊と子狸は、とにかく何かを掴み取りたいのだ。それは栄光や成功ではなく、あくまでもニジマスでありイワナである。
ただ問題は「池を自由に動き回る魚を捕まえることなど、野生の熊でもなければ到底できない所業である」ということなのだ。案の定、開始5分で子狸次男はギブアップし、早々にニジマス釣りへと方針転換。こちらはこちらで入れ喰いのため、5分も経たないうちに3匹連れてしまった。
対する浣熊はというと、こちらは熱中集中奮闘中。網を両手に持った宮本武蔵スタイルで、諦めることなく魚を追っていた。何分楽しもうと料金は同じなので、死闘を続ける長男をそのままに私はニジマスの塩焼きを発注した。
5分後、何やらつかみ取り池で歓声があがる。ふと視線を向けると、その中心にいたのは何を隠そう我が家の浣熊だった。
「捕まえた」と自慢げに言う浣熊の掲げる網の中には、神々しく光を放つ一匹のイワナが「何すんねんお前!」とご立腹の様子でバタバタと尾びれを動かしていた。
興奮気味にイワナを捕まえた際の状況を説明する浣熊だったが、生来の説明下手のため、何を言っているのかよくわからない。
「とにかくよくやった!」
私は浣熊の偉業を褒め称え、700円の巨費を投じて追加のイワナ塩焼きを発注した。
満足気に焼き上がったニジマスとイワナの両方にかぶりつく浣熊の笑顔を見て、子どもの成長と時の流れの早さを感じる夏の日の出来事だった。
祭エンジン賞
- 祭グッズ
私は縁あってこの4月から広島で生活している。
広島は、世界で初めての被爆地であり、それ故に平和への祈りを強く感じることの出来る街だと感じる。
暑い夏の日、歩いていると、平和学習の一貫だろうか、小学校から「折り鶴」が流れてきた。
聴くのは約20年振りだ。
懐かしいな、と思うと同時に祖父の顔が浮かんだ。
広島は私の祖父の生まれ故郷でもある。
私にとって祖父は、博識で料理上手、絵も上手く達筆で、バイタリティがある多彩な人だ。
祖父の焼く甘く太い卵焼きは絶品で、子供の頃はこれがおやつだった。
私が絵画コンクールで賞をとっても同じ景色を描いた祖父の荘厳で個性のある絵を見て幼心に「敵わない」と思ったものだ。
それでも祖父はいつもどんな時も私を褒めてくれた。
私は昨年息子を出産し、母となった。
広島に来て、今なお残る戦時下の惨状の名残を目の当たりにし、この地に確かに存在した、私の知らない幼き日の祖父を想う。
私が知っているのは「孫の私を溺愛する多彩な祖父」だが、祖父にも息子と同じ頃があり、だけどそれは今とはかけ離れた環境だった。
明日生きることを考え、逞しく生きなければならなかった、そんな時代を想う。
そういう時代を乗り越えてきたから今、私達はここにいるということも。
今年の夏は、平和を人生で一番尊く、そして身近に感じられた。
息子の生きる次世代まで繋いでいきたいという新しい感情にも出会った。
私は、ここ広島で、祖父や、その先にいる先祖の人達とその人達が生きた場所のルーツを辿りたいと思っている。
私達の命はどこからきて、その人達はどういう時代をどんな想いで生きて、今の私達にその血が流れているのか。
命のリレーの歴史を辿り、そのバトンを息子と、その先に託したい。
親子の日賞
- 親子の日オリジナルグッズ
その当時、私は、主人の転勤先の大阪で暮らしていた。
慣れない土地、実家は遠く、主人は営業職で日をまたいで帰宅することも多かった。
いわゆるワンオペ状態。
幼い息子はよく熱を出す子どもだった。
その日はとても眠かった。
昨夜も主人の帰宅は遅く、片付けは日をまたいだ。
「寝てていいよ」と言われても、当時は帰りを待って起きていた。
昼寝をしていた息子が目を覚ました。
確か3歳ごろだったと思う。
「かぁか、おきて!すべりだいしたい!」
私は眠くて「もう少しねんね」と返すと、「けんちゃん、ねむくない。おさんぽ行こうよ」と迫ってくる。
「冷蔵庫にプリンあるよ」と言うと、息子は上手に食べ、再び誘いに来た。
まだ寝たい私は、「頭が痛いの。お熱もあるの。トミカのビデオ観てて」と言ってみた。本当は、頭痛も熱もない。仮病を装った。
息子は静かになり、私の側を離れた。
これで20分は寝られると思ったとき、額に冷たいものが。
「かぁかのあたま、いたいのいたいのとんでいけ!これでおねつさがるよ」
息子は冷蔵庫から熱冷ましシートを取り、私に貼ってくれた。
小さな椅子が冷蔵庫の前にあった。
よいしょ、よいしょと運び、背伸びして取った姿が浮かぶ。
静かに涙が出た。罪悪感と、成長への感動で。
「けんちゃん、ありがとう!もう治ったよ。
お散歩行こう。
かぁか今から用意するから待っててね」
玄関で靴を履いた待っていた息子がつぶやいた。
「かぁか、おっそいなぁ。いつまで待たせるんだよぉ」
まさしく主人の口調。
大笑いした。
子どもは親をよく見ている。
小さな手を握り、外へ出た。
もうすぐ二十九歳になる息子。
父親になる日は近いだろう。
きっと優しい父親になると思う。
ただし、お嫁さんの支度はゆっくり待ってあげてね。
大きなうさぎの絵が描かれた、クリーム色のベビー毛布。
不安なとき、叱られたとき、魔法の絨毯のようにぱっと広げて、ひなたぼっこするひとときは至福だった。
次第に睡魔に襲われて、瞼を閉じて、すうすうすう……。
うたた寝から目覚めると、いつもうさちゃん毛布がかかっていた。ほんのり甘いカステラのように、ふんわりと。
「かけてもすぐにはいじゃうんだもの。そのたびにかけ直してあげてね。あー、かわいかったわ」
母が頬を緩めて、当時の面影を探るように私の顔を覗き込んでくる。
きっと、毛布の心地よさは、柔らかい肌触りによるものだけでなかろう。母の深い愛情が染み込んで、ぬくもりが倍増して、丸ごと包みこんでくれるように感じられたのだと思う。
長い間使い続けるにつれて、日に焼けて色落ちしてしまった。石鹸で落としきれないシミもいくつかついた。
それでも捨てずに、クローゼットの手前のハンガーにずっとかけていた。
近くにあるだけで、そばに寄り添ってくれているようで、不思議と心が安らいで幸せな気持ちになれた。
久しぶりに毛布を介して母の愛に浸りつつ、となりで大きな鼾をかく娘をじっと見守る。
「まったく、すぐ蹴飛ばしちゃうんだもん。風邪引くといけないから、ちゃんとかけようね」
実家の窓辺で寛ぎながら、水玉模様のブラウスの裾を下ろしておへそを隠す。そして、娘の大好きなイルカ柄のベビー毛布をかけ直して、子守唄を口ずさんでみる。
「いっしょに休憩しよっかな」
お腹に懐かしのうさちゃん毛布をかけて寝そべって、ミノムシのように腰を丸めた。
娘と同じ格好でぽかんと口を開けて、すやすやすや……。
よく食べよく遊び、十分休んで、元気に育ってね。
娘の健やかな成長を願いながら、めくるめく毛布の魔法にかけられていく。
私は、或る日から家族旅行に行かなくなった。
大学受験のために机にかじりついていた……いや、そういう理屈をつけていただけかもしれない。
本当のところは、ただ家族と連れ立って喧しい場所へ赴くことに、理由が見いだせなくなったのだ。
――つまり、静けさが欲しかったのである。
家族は黙ってそれを受け入れた。やがて私を残して出かける旅の数が、少しずつ増えていった。
きっと、私が「静謐」を欲しているのを見透かしたのだろう。
私の家には静寂など、もとより存在しない。
テレビはいつも鳴り、笑い声が壁を揺らし、換気扇が唸り、エアコンが呻く。
家の隅のさらに隅にうずくまっても、ざわめきは追ってくるのだ。
――だが、家族がいなくなると、不意に訪れる。
空虚なほどの静けさが。
音もなく残されたこの体は、奇妙な解放に似た感覚を味わう。
部屋の隅から隅へと広がる空気は「シン」と澄むというより、「パキッ」と割れそうな緊張を孕んでいて、私はそれと一つになろうとする。
このまま、ずっと……静けさのうちに生きていたい――。
……そう思うのは、最初の三時間ばかりだ。
やがて、静寂は耳鳴りに変わり、シャリシャリと蝕むような幻聴を呼び寄せる。
私は気分が悪くなり、結局はテレビをつけ、音楽をかけ……
――ああ、帰ってきてくれ。
玄関が開くと、ドタバタと音が流れ込む。
笑い声が跳ね、食器の触れ合う音がひびき、テレビが無遠慮に騒ぎだす。
私は眉をひそめつつも、胸の奥では安堵している。
静けさは確かに私を慰める。
けれど、ざわめきこそが、私を何かとつなぎとめる。
「親子の日」というものがあるらしい。
私はその日を、花を贈る日でも、特別な言葉を交わす日でもなく、
ただ――ざわめきのありがたさを思い知る日として迎えたい。
ひとりでは味わえぬ不自由。
親と子とが交わることで生まれる不調和。
その不調和こそが、私にとっての生活であり、安らぎであり、
――帰るべき場所なのだ。
私はこの春から医師として働き始めた。
中高と私立の学校に通わせてもらった上に、浪人や留学も経験させてもらい、気づけば28歳でようやく社会に出ることになった。
遂に手にした初任給。
母に、「何か欲しいものある?」と尋ねると、「何もいらないから、家の庭の草取りをしてほしい」と笑われた。
ゴールデンウィークに実家に帰省した際、私は母の言葉を思い出し、実に、小学生ぶりとなる草取りに精を出した。
青春時代をテストに追われて過ごしていた自分の体には、5月の陽ざしさえまぶしく、ずいぶんとこたえた。これを母は、私が机に向かっていた頃、何も言わずに一人で全部やってくれていたんだなと思うと、胸の奥まで日焼けしてしまいそうな思いだった。
医師になってまず最初に、私は師匠に、「患者さんは自分の親を見るように診なさい」と教わった。人と向き合ううえで本当に大切なのは、相手が求めていること、ニーズに耳を傾け、それに応えること。
母への草取りも、医療の現場も、その根っこは同じなんだなと感じた。
あの日、草取りの後に言われた母からの「ありがとう」は、今も白衣の内側で、どこか消化不良のまま引っかかっている。
八十九歳の母をひとり実家に残し、六十一歳で医師を辞め、私はオランダへ渡った。小説家になりたいという、子どもの頃から抱き続けてきた夢を、ようやく追う決意をしたのだ。
母は、そんな私をすぐには許さなかった。「こんな年寄りば一人のごして、遠い異国へ行ぐなんて!」。届く手紙は、たいてい同じ文句で始まり、同じ不安で結ばれていた。父は七十一歳でこの世を去り、その最期を主治医として看取った私に、母もまた、自らの終焉を託そうとしていたのだろう。その気持ちは痛いほどわかった。だが、それでも私は行きたかった。夢の続きを、書きたかった。
ある日、母の文面がふと変わった。「あんだ、小さい頃、いつも物語を書いでだねえ」。唐突な一文だった。思い返せば、私は子どものころから、紙と鉛筆があればどこにいても、世界を創ることができた。机にかじりついて言葉を綴る私の姿が、若き日の父と重なったのだと、母は言った。
父は医師でありながら、詩や小説を愛する人だった。診察の合間に本を読み、時にノートに何かをしたためていたという。作家になる夢を、いつしか白衣に包んで封じた人。その夢を、私が知らず知らず継いでいたのかもしれない。
母はついに言った。「おとうさんの夢を、あんだが継ぐがね。なら、もうしかだないべなや」。旅立ちの朝、私のバッグの隅に、小さな封筒が入っていた。「気をつげでいがいよ。あんだの夢も、おとうさんの夢も、応援してっから」。震える文字に、私は声を上げて泣いた。
夢とは、個人のものに見えて、実は誰かの記憶や願いを織り込んだ継承なのかもしれない。母の許しが、私の一歩になった。そして今も、遠い国で書く私の背中を、母の静かな祈りが支えてくれている。
あれは、昔、五月の母の日だったね。
帰郷し、何か欲しいものがあるかと尋ねたら、杖が欲しいとの答えだった。
年老いたあなたは、足腰が随分弱くなり、歩くのも大変な様子になっていた。一緒に店へ行き、母さんが選んだのは、安価で地味な木の杖だった。もっと高級なものにしたら、と言ったら、目立たないから、これが良いと、小さな声で言った。
その後、しばらくご無沙汰して、久しぶりに帰ったら、母さんの杖が一目でわかるほど短くなっていた。どうしたのかと尋ねたら、長いので自分で切ったと、あなたは答えた。血圧が高く心臓に持病を持つ母さん、鋸を使うのは、容易なことではなかった筈だ。それは、私のやるべき仕事だ。ご無沙汰が、母さんに病に障るような負担をかけてしまった。
そんなに長さが合わないことに気づかなかった、私が馬鹿だった。それとともに、苦労が多かった母さんの生涯を思った。父さんが、前の奥さんと比べてあなたを嫌った。思い詰めたあなたは、真夜中、私を連れて線路端へ行き、死を決意したこともあった。しかし、父さんが大病をした時に献身的に看護し、父さんのあなたへの態度が別人のようにやさしくなった。定年まで勤めた教師も、つらいことが多かったようだね。僕達家族の為に、そのような苦労をした為に、腰がひどく曲がってしまったから、短かい方が良かったのだね。
父母の死後、いずれ使う時もあろうかと考えて、故郷の空き家から持ってきた、母さんの古い杖。私も、高齢になり、膝が悪くなり、ひっくり返らぬよう、使い始めた。短いけれど、敢えてこの杖を使う。新しいものを買い求めるつもりはない。この杖をついて、ゆっくり歩く母さん。この杖には、母の心がしみ込んでいる。その杖をつきつつ、私もゆっくり歩く。あなたのことを偲びながら。短いけれど、転ぶことはなくなった。死後も、転びそうな私を支えてくれる。死後も、老い衰えた私を守ってくれる。ありがとう、母さん!